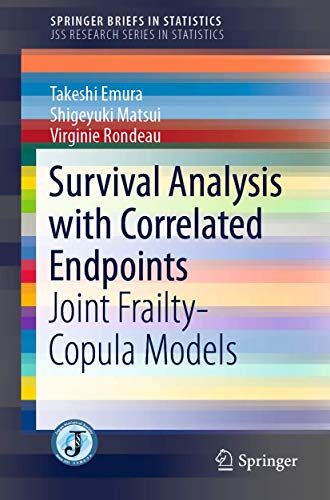前回、「Joint Frailty-Copula Modelを使った生存時間解析」の理論的なことについてまとめました。
読んだ本:
今回は、上記の著者が作成したjoint.Coxパッケージを使って、Rで解析を実行する方法をまとめたいと思います。
ベースラインハザード関数の表し方
このパッケージでは、ベースラインハザード関数を表すために、
- 3次M-スプライン(cubic M-spline)を用いたノンパラメトリックモデル
- ワイブル分布(Weibull distribution)を用いたパラメトリックモデル
のどちらかを用いることができます。
M-スプラインは定義域で非負が保証されているスプラインで、自由度の高い曲線を当てはめることができる代わりに、パラメトリックモデルよりも計算負荷が高くなります。
ワイブル分布については、以前まとめた記事を参考にしてください。
jointCox.reg( )でM-スプラインを用いる方法
指定する引数は以下のとおり。
event:「腫瘍増悪」のように、必ずしも観察終了とはならないイベント(non-terminal event)の発生有無(1=発生, 0=非発生)t.event:non-terminal eventまでの時間death:「死亡」のように、強制的に観察終了となってしまうイベント(terminal event)の発生有無(1=発生, 0=非発生)t.death:terminal eventまでの時間Z1:non-terminal eventに関連する共変量を行列形式で指定(Z1の列数=共変量の個数)Z2:Z1と同様に、terminal eventに関連する共変量group:所属するクラスターを指定する変数alpha:イベントごとにフレイリティ項を変更するかどうか(0=同じフレイリティ項を使用, 1=異なるフレイリティを使用)*1
スプラインを使う場合は「どの程度の滑らかさにするか」を示すパラメータ(smoothing parameter)を、以下のLikelihood cross-validation(LCV)を最大にするように決めます。
LCV = 対数尤度(当てはまりの良さ)- モデルの複雑さ(罰則)
2つのイベントを同時に考えてLCVを最大化するのは計算負荷が大きいそうで、それぞれのイベントについてLCV1, LCV2を最大にするようにsmoothing parameterを決めます。
このときsmoothing parameterを探索する範囲をkappa1, kappa2で指定できますが、正直どれくらいにしたらいいのか分からないのでデフォルトの設定を使うことにします。
では、joint.Coxパッケージに付属の卵巣腫瘍のデータ(dataOvarian)を使って試してみます。
library(tidyverse) library(joint.Cox) data(dataOvarian)
サンプルデータの中身:
> dataOvarian %>% glimpse Rows: 1,003 Columns: 6 $ t.event <int> 1650, 30, 720, 450, 510, 1110, 210, 1380, 1800… $ event <dbl> 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0… $ t.death <int> 1650, 30, 720, 780, 990, 1110, 600, 1410, 1800… $ death <dbl> 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0… $ group <dbl> 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4… $ CXCL12 <dbl> 1.30594160, 1.28621637, -1.36903145, 1.6132696…
これをjointCox.reg( )に渡します。計算の過程で "Error in integrate..." が出続けますが無視していいとのこと。
result <- jointCox.reg( t.event = dataOvarian$t.event, event = dataOvarian$event, t.death = dataOvarian$t.death, death = dataOvarian$death, Z1 = dataOvarian$CXCL12, Z2 = dataOvarian$CXCL12, group = dataOvarian$group, alpha = 0 )
出力結果
結果は以下の項目が一括で表示されます。少しずつ見ていきます。
まずは使用したデータのイベント数をまとめたもの。
> result $count No.of samples No.of events No.of deaths No.of censors 4 110 76 46 64 8 58 48 36 22 11 278 185 113 165 14 557 266 290 267
次に、共変量(ここではCXCL12)に対する係数とその信頼区間。
$beta1 estimate SE Lower Upper 0.19897418 0.03580646 0.12879353 0.26915484 $beta2 estimate SE Lower Upper 0.16540746 0.04234325 0.08241470 0.24840023
η(イータ)はフレイルティ項の分散の推定値。
$eta estimate SE Lower Upper 0.033275908 0.029043661 0.006014176 0.184112694
θはコピュラのパラメータです。どうやらクレイトンコピュラのみ使用可みたいです。
τはケンドールの順位相関係数で、クレイトンコピュラでは で計算されます(この出力でもそのようになっていることを確認)。
$theta estimate SE Lower Upper 2.3632714 0.2354481 1.9440548 2.8728881 $tau estimate tau_se Lower Upper 0.54162833 0.02473436 0.49290765 0.58956578
LCVを最大にするκとそのときのLCV(だと思います)。
$LCV1 K1 LCV1 3.103448e+16 -4.591487e+03 $LCV2 K2 LCV2 3.448276e+16 -4.159568e+03
M-スプラインの係数です。gはeventのベースラインハザード関数、hはdeathのそれを表すのに使います(詳細は後ほど)。
$g
[1] 9.136547e-01 1.686345e+00 1.855953e-97 4.447143e-02 8.208009e-155
$h
[1] 2.121898e-01 1.083565e+00 9.906754e-01 1.763836e-01 3.368575e-94
$g_var
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 0.0044487471 -0.0027831825 0.00000e+00 -0.0003813422 0.000000e+00
[2,] -0.0027831825 0.0248178870 0.00000e+00 0.0008556739 0.000000e+00
[3,] 0.0000000000 0.0000000000 3.44456e-190 0.0000000000 0.000000e+00
[4,] -0.0003813422 0.0008556739 0.00000e+00 0.0524971946 0.000000e+00
[5,] 0.0000000000 0.0000000000 0.00000e+00 0.0000000000 6.737141e-305
$h_var
[,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 9.506484e-04 -0.0013733137 -3.285041e-06 -2.162385e-04 0.000000e+00
[2,] -1.373314e-03 0.0099792406 -1.177544e-02 -1.839687e-04 0.000000e+00
[3,] -3.285041e-06 -0.0117754352 5.668603e-02 -9.863048e-05 0.000000e+00
[4,] -2.162385e-04 -0.0001839687 -9.863048e-05 4.356045e-02 0.000000e+00
[5,] 0.000000e+00 0.0000000000 0.000000e+00 0.000000e+00 1.134729e-183
最後に収束状況全般について。
$convergence MPL DF LCV code No.of.iterations No.of.randomizations -8604.369 20.000 -8618.603 1.000 91.000 10.000 $convergence.parameters NULL
ベースラインハザード関数を描く
推定されたスプラインの係数(g, h)から、スプライン曲線を描くことができます。
ここで使われているM-スプラインは、負にならないスプラインです。M-スプラインでは、隣接する区域の基底関数を使って再帰的に目的の次元(ここでは3次)の基底関数が作られます。
本を読むと、
:最小のイベント発生時間
:
:最大のフォローアップ期間
の3つが内在するノットに設定されています。
内在ノット数3で3次のMスプラインを定義すると、基底関数は5つ必要になる*2そうで、この基底関数の係数がgやhとして与えられているようです。
joint.CoxパッケージにあるM.spline( )関数を使って、5つの基底関数を求めることができます。
M.spline(time, t_min, t_max)
以下の3つの引数を指定して使います。
time:対象区間の時点をベクトル形式で指定(例:time = c(1,2,3,4,5)など)。t_min,t_maxの範囲に収まっている必要あり。t_min:時点の下限。non-terminal event発生までの時間の最小値を指定。t_max:時点の上限。terminal event発生までの時間の最大値を指定*3。
例にならって下のように指定します。
t_min = min(dataOvarian$t.event) t_max = max(dataOvarian$t.death)
ベースラインハザード関数を書くときは、M.spline( )に実際の時点を与えるのではなく、関数式として定義してcurve( )に渡します。
# 平均線 r1_func = function(t){as.numeric(M.spline(t, t_min, t_max)%*%(result$g))} # 95%信頼区間の下端 r1_low_func = function(t){ M_vec = M.spline(t, t_min, t_max) r1_V = M_vec%*%(result$g_var)%*%t(M_vec) as.numeric(M_vec%*%(result$g) - 1.96*sqrt(diag(r1_V))) } # 95%信頼区間の上端 r1_upp_func = function(t){ M_vec = M.spline(t, t_min, t_max) r1_V = M_vec%*%(result$g_var)%*%t(M_vec) as.numeric(M_vec%*%(result$g) + 1.96*sqrt(diag(r1_V))) }
平均の線はM.spline( )で作成した5つの基底関数と、モデルの当てはめで推定したスプラインの係数(g)との積を計算した式を定義しています。
信頼区間の場合は、スプラインの係数の共分散行列(g_var)を使って標準誤差を求めて、mean±1.96*SEとして計算した式を定義しています。
これを下のコードで重ね描きすると、
curve(r1_func, from=t_min, to=t_max) curve(r1_low_func, from=t_min, to=t_max, lty="dotted", add=TRUE) curve(r1_upp_func, from=t_min, to=t_max, lty="dotted", add=TRUE)
となります。軸ラベルや範囲は適宜指定してください。
jointCox.Weibull.reg( )でワイブル分布を用いる方法
ベースラインハザード関数にワイブル分布を使う場合は、jointCox.Weibull.reg( )を使います。 指定する主な引数はjointCox.reg( )と同じです。
result <- jointCox.Weibull.reg( t.event = dataOvarian$t.event, event = dataOvarian$event, t.death = dataOvarian$t.death, death = dataOvarian$death, Z1 = dataOvarian$CXCL12, Z2 = dataOvarian$CXCL12, group = dataOvarian$group, alpha = 0 )
出力結果
出力結果を見ていきましょう(一部省略しています)。
Mスプラインを使ったときと、概ね同じようなβが推定されました。フライリティ項の分散は少し大きくなりました。
$beta1 estimate SE Lower Upper 0.22058618 0.03912474 0.14390170 0.29727067 $beta2 estimate SE Lower Upper 0.17069401 0.04460975 0.08325891 0.25812912 $eta Estimate SE Lower Upper 0.09406251 0.06685348 0.02335754 0.37879662
クレイトンコピュラのパラメータθと、そこから求められるケンドールのτも値が少し変わりました。
$theta Estimate SE Lower Upper 1.7017831 0.1951057 1.3592960 2.1305630 $tau Estimate SE Lower Upper 0.45971983 0.02847593 0.40463716 0.51580451
イベント1, イベント2のそれぞれのベースラインハザードについて、ワイブル分布の尺度パラメータ(scale)と形状パラメータ(shape1)が推定されています。
$scale1
Estimate SE Lower Upper
0.0006696365 0.0001630500 0.0004155048 0.0010792008
$shape1
Estimate SE Lower Upper
1.10866686 0.03383253 1.04429928 1.17700187
$scale2
Estimate SE Lower Upper
4.544557e-05 1.563874e-05 2.315104e-05 8.920982e-05
$shape2
Estimate SE Lower Upper
1.31537842 0.04662033 1.22710415 1.41000287
ベースラインハザード関数を描く
推定されたワイブル分布の尺度パラメータと形状パラメータを取り出します。
scale = result$scale1[1] shape = result$shape1[1]
密度関数にワイブル分布を使ったときのハザード関数は、
なので、下のコードのようにう関数を記述し、curve( )で描いてみます(dweibull( )とpweibull( )を使っても書けると思いますが、かえってコードが長くなりそうなので)。
r1_func_weibull <- function(t){(shape/scale)*(t/scale)^(shape-1)} curve(r1_func_weibull, from=t_min, to=t_max)
出来たグラフは下のとおりなんですが...
M-スプラインで描いたときとあまりに違うので、どこか間違えているのかも...。
おわりに
- 「Rで実行する方法をまとめてみたいと思います!」と意気込んだ割に、コードの意味を表面的になぞるだけになってしまいました。
- GJRMというパッケージを使うともう少し自由度が高い joint model も扱えるっぽいです。
- NHK「おれ、ねこ」の投稿用写真を選んでます。療養食なので「いつものご飯」と「スペシャルご飯」が同じになってしまう...。
参考資料
- M-スプラインの話ではないですが、スプライン補間とは何かについて5回シリーズで詳しく解説してくださっています。私のような疫学分野の末端ユーザーでは、局面まで拡大する機会はないでしょうし、難しくて理解しきれなかったところもありますが、とても面白く読ませていただきました。